医療的ケアが必要なお子さんの育児は、本当に大変ですよね。毎日、目まぐるしい日々の中で、お子さんのケアはもちろん、家事や他のご家族のことまで、全部一人で背負っているように感じているパパ・ママもいらっしゃるかもしれません。
「あれ、この症状、大丈夫かな?」、「この制度、うちも使えるのかな?」と、ふと不安になることはありませんか?インターネットで検索しても、情報が多すぎて何が正しいか分からなかったり、どこで情報を得ればいいか迷ってしまうこと、ありますよね。
この情報迷子状態、私たちも経験があります。でも、もう大丈夫!この記事を読めば、あなたに必要な情報をスムーズに見つけられるようになり、迷うことなく進めるようになるはずです。
なぜ情報が必要なのか
医療的ケアが必要なお子さんの育児は、一般的な育児とは少し違いますよね。ミルクをあげるだけでなく、吸引をしたり、チューブを通して栄養を摂ったり、医療機器の管理をしたり…。そのため、普通の育児情報だけでは、どうしてもカバーしきれない部分があります。
- 急な発熱や体調変化の時、どうしたらいいのか?
- 利用できる制度やサービスは何があるのか?
- 同じような状況のお子さんを持つパパ・ママたちは、どうしているのか?
- 適切なケアが遅れて、お子さんの症状が悪化してしまうかもしれません。
- 使えるはずの制度を知らず、経済的にも精神的にも負担が増えてしまうかもしれません。
- 一人で抱え込んでしまい、孤独を感じてしまうかもしれません。
特に、育児中は、ただでさえ自分の時間が少ないのに、情報収集に時間をとられてしまうと、心も体も疲れ果ててしまいますよね。不確かな情報に振り回されて、不安な気持ちになることもあるかもしれません。そして、その不安がお子さんの成長に影響するんじゃないか、と心配になることもあるかもしれません。
だからこそ、必要な情報をしっかり手に入れることは、パパ・ママにとっても、お子さんにとっても、とても大切なんです。
どこで情報を得るか

「じゃあ、どこで情報を集めればいいの?」と、思われたかもしれません。私たちも全てを利用したわけではありませんが、医療的ケア児のパパ・ママをサポートする上では、様々な情報源があることを知っておくことも大切だと考えていますので、それぞれご紹介させていただきます。
医療機関・医療従事者
①主治医の先生
一番身近で頼れるのが、主治医の先生です。お子さんの状態を一番よく知っていますし、最新の医療情報も教えてもらえます。診察の時に、疑問に思っていることや不安なことを、遠慮なく聞いてみてください。
②看護師さん
日々のケアで困ったことがあれば、看護師さんが心強い味方になってくれます。吸引の仕方、薬の使い方など、具体的なアドバイスをもらえます。また、緊急時の対応についても、事前に確認しておくと安心です。
③リハビリの先生(PT・OT・ST)
お子さんの発達や機能で気になることがあれば、リハビリの先生に相談してみましょう。専門的な視点から、適切なアドバイスをもらえます。
④薬剤師さん
お薬について不安なことがあれば、薬剤師さんに相談しましょう。薬の飲み方、副作用など、正しい情報を教えてくれます。
⑤ソーシャルワーカーさん
利用できる制度や福祉サービスについて、相談に乗ってくれます。お金のこと、生活のこと、困ったことがあれば頼ってみましょう。
患者会・親の会
同じ病気や境遇を持つご家族と繋がれるのが、患者会や親の会です。「うちの子も同じことで悩んでいる」、「こんなケア方法を試してみたらうまくいった」など、インターネットでは得られない、生きた情報を交換できます。孤独を感じやすい育児の中で、同じ気持ちを共有できる仲間がいることは、とても心強いものです。今は、オンラインで参加できる会も増えていますので、ぜひ探してみてください。
▼以下のサイトも参考になります。
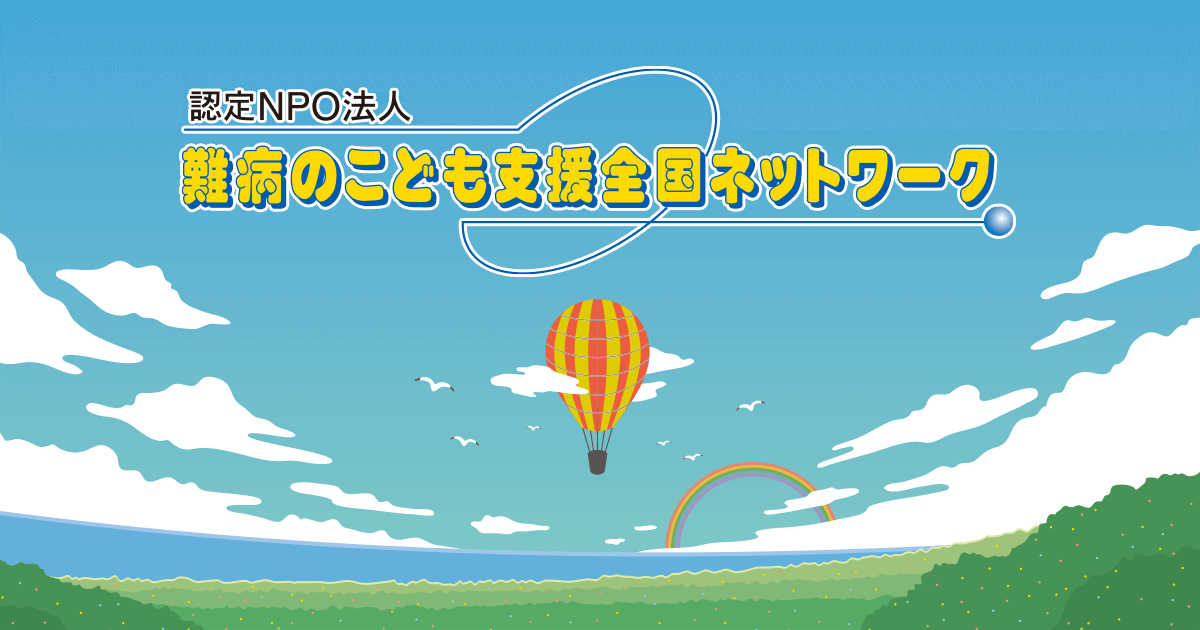
インターネット・SNS
インターネットは検索ワードを工夫したり、「信頼できる情報源」を意識して検索したりすることが大切です。SNSは同じ境遇のパパ・ママたちが集まるグループに参加するのもおすすめです。体験談を読んだり、質問をしたりすることで、役立つ情報を得られます。ただし、SNSの情報は玉石混交。信頼できる情報を見極めるように注意しましょう。
私たちもInstagramで2024年4月から「関西会」という交流会を不定期ですが開催しています。
(お花見、バーベキュー、ハンドメイド作品の販売会、単なるおしゃべり会など)
興味のある方はInstagramのDMでもメッセージでも結構ですので気軽にお声かけください。
その他
医療的ケア児とその家族を支援する団体(支援団体・NPO法人)もたくさんあります。相談窓口で話を聞いてもらったり、必要な情報を教えてもらったり、さまざまなサービスを受けることができます。
また、お住まいの市区町村の福祉課や保健センターでも、相談することができます。利用できる制度やサービスの情報を教えてもらえます。「どこに相談すればいいか分からない…」「何から聞けばいいのか分からない…」という場合も、まずは行政機関に連絡してみるのがおすすめです。
情報収集のコツ

必要な情報源が分かったら、次は情報を効率よく集めるためのコツをお伝えします。
目的を明確に!
まず、「何を知りたいか」「どんな情報を求めているか」を具体的に考えてみましょう。例えば、「吸引器の使い方を知りたい」「保育園を探したい」など、目的を明確にするほど、情報収集がスムーズになります。
複数の情報源を比較!
1つの情報だけを鵜呑みにせず、複数の情報源を比較することが大切です。複数の情報を確認することで、より正確な情報を得ることができます。特に、医療系の情報は、信頼できる情報源(病院のウェブサイト、専門家の意見など)を確認するように心がけましょう。
情報を整理!
集めた情報は、メモアプリや手帳などに整理しましょう。情報をカテゴリー分けしておくと、必要な時にすぐに見つけられます。
- 医療情報:医師からの説明、薬の情報など
- 制度情報:利用できる制度、手続き方法など
- ケア情報:日々のケア、グッズの情報など
スキマ時間を活用!
育児中は、自分の時間がない!という方も多いかと思います。そんな時は、細切れ時間を活用してみましょう。例えば、お子さんが寝ている間や、移動中などにスマホで情報収集をすることができます。また、他のご家族にも協力してもらって、情報収集の時間を作ってもらうのも良いでしょう。
情報収集の注意点
①情報の信憑性を確認する
インターネットの情報の中には、間違った情報や古い情報も紛れています。情報の出どころがはっきりしているか、信頼できる情報源なのか、必ず確認しましょう。
②情報過多にならないように
インターネットで検索していると、次から次へと情報が出てきて、疲れ切ってしまうこともあるかもしれません。情報に振り回されてしまわないように、自分に必要な情報を見極めることが大切です。
③不安を煽るような情報に惑わされない
中には、不安を煽るような情報もあります。そういった情報に触れてしまうと、余計に不安になってしまうことがありますので、触れないようにしましょう。
まとめ
いかがでしたか?この記事では、医療的ケア児のパパ・ママが「必要な情報」をスムーズに得るための情報源とコツをお伝えしました。この記事で紹介したことを参考に、あなたに必要な情報を、安心して手に入れてくださいね。あなたは決して一人ではありません。困ったことがあれば、いつでもご相談ください!
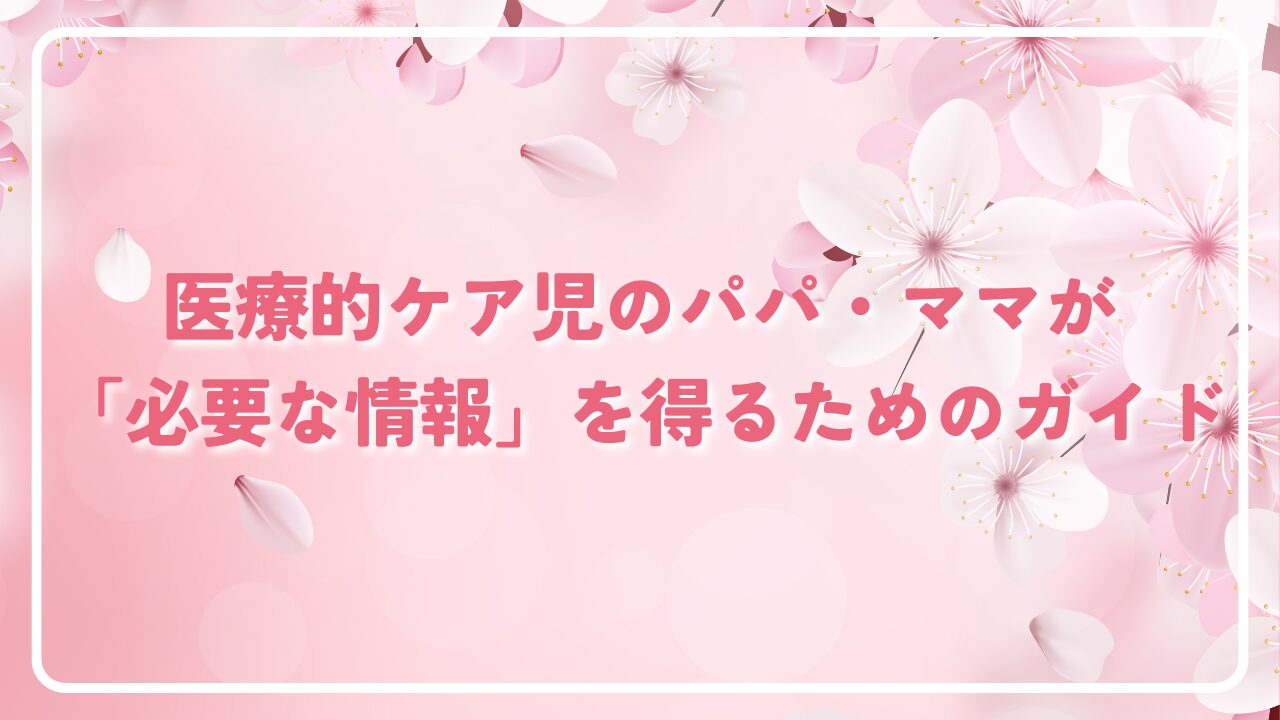
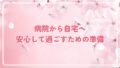
コメント