退院が決まった時、嬉しさとともに、不安を感じたかもしれません。「本当に退院して大丈夫だろうか」「医療的ケアは自分たちにできるのだろうか」と、退院後の生活に戸惑うと思います。でも全国にはたくさんの医療的ケア児家族がいて、皆さんがそれぞれのペースで自宅でのケアを頑張っています。
私たちはそういったご家族の存在を知っていたからこそ、「きっと自分たちもできる!」と、どこか確信めいたものがありました。例えば自転車や車の運転ができる人が多いように、医療的ケアも特別なことではなく、きっと誰でもできることだと感じていました。
この記事では、私たちが実際に経験したことや、後から知って「もっと早く知りたかった」と思った情報も含めて、在宅看護への移行で悩んでいるパパ・ママへ向けて、少しでもお役に立てるような情報を共有したいと思います。
入院中に準備すべきこと

入院中にできる準備はたくさんあります。退院後の生活をスムーズにスタートさせるために、医師や看護師、医療ソーシャルワーカーと連携し、具体的な計画を立てていきましょう。この時期にしっかりと準備しておくことで、退院後の不安を少しでも軽減できるはずです。
医師や看護師との相談(退院後のケアプラン作成)
退院後のケアプランは、まるで航海図のようなものです。医師や看護師とじっくり話し合い、病状や必要な医療的ケア、今後の見通しなどを明確にしましょう。わからないことは遠慮せずに質問し、不安な点は全て解消しておくことが大切です。ケアプランは、後々、訪問看護ステーションや相談支援専門員と連携する上でも重要な情報となります。自分たちの想いを伝え、納得のいくプランを作成できるようにしましょう。
私たちは退院後のリハビリ計画、訪問看護の頻度、緊急時の対応などを細かく確認しました。
訪問診療・訪問看護の準備
訪問診療や訪問看護は、退院後の生活を支える大きな力となります。私たちの場合は、訪問看護ステーションのスタッフが入院中の病院に足を運んでくれました。実際に会って話すことで、どんなサポートが受けられるのかを具体的に知ることができました。また、医師の指示書が必要ですので、早めに相談しておくのがおすすめです。
訪問看護の利用は、医療的ケアだけでなく、家族の心のケアにも繋がります。信頼できる訪問看護ステーションを見つけることで、在宅での生活がより安心なものとなるはずです。
必要な福祉用具や機器の選定(吸引器、酸素濃縮器など)
吸引器や酸素濃縮器など、医療的ケアに必要な福祉用具や機器は、退院前に準備しておきましょう。私たちは、病院の相談員に確認しながら、購入やレンタルに関する情報を収集しました。助成制度もあるので事前に確認しておくと、費用負担を軽減することができます。
また、これらの機器の操作方法についても、病院でしっかりと指導を受けておくことが大切です。自宅でスムーズにケアできるよう、退院前に練習しておきましょう。
自宅での看護体制を整える

自宅での看護体制を整えることは、夫婦で取り組む一大プロジェクトです。それぞれの役割を決め、連携を取りながら、お子さんの成長を支えていきましょう。大変なこともたくさんありますが、家族の絆を深める良い機会にもなるはずです。
家族間での役割分担
在宅看護は、決して一人で抱え込まず、家族みんなで協力することが大切です。それぞれの得意なことや時間に合わせて、役割分担を決めましょう。例えば、お父さんは医療機器の管理や買い出し、お母さんは食事の準備や入浴介助、お兄ちゃんはお子さんの遊び相手、というように、無理のない範囲で役割を決めて、負担を分散させることが重要です。
また、定期的に役割の見直しを行い、家族の状況に合わせて調整することも必要です。
家族で話し合い、それぞれの力を合わせて、お子さんをサポートしていきましょう。
相談支援事業所や医療的ケア児支援制度を活用する
相談支援事業所は、在宅看護をする上で、とても頼りになる存在です。医療的ケア児を対象とした支援制度は、情報収集が難しい場合もあるので、積極的に活用しましょう。相談支援専門員は、福祉サービスの情報提供だけでなく、申請手続きのサポートもしてくれます。
困ったことや分からないことがあれば、ぜひ相談してみてください。
一人で悩まず、専門家の力を借りることで、安心して在宅看護を続けることができます。
私たちは在宅看護を始めた当初、相談支援事業所を利用していませんでしたが、それでも何とか日々の生活を送ることができていました。在宅での生活が少し落ち着いてきた頃、保育園への通園が難しいため、訪問保育の利用を申請する際に、相談支援員の方に個別支援計画書を作成してもらったことが、相談支援事業所との最初の接点でした。
定期的な医療チェックと緊急時対応の準備
自宅での看護では、定期的な医療チェックと緊急時対応の準備が不可欠です。訪問看護師や医師と連携を取り、定期的な健康状態のチェックを欠かさないようにしましょう。また、緊急時に備えて、連絡先リストや救急搬送時の手順などをまとめておくと安心です。万が一の事態に、冷静に対応できるよう、日頃からの準備が大切です。
在宅看護における公的支援制度の活用

在宅看護を継続していく上で、公的支援制度はとても重要です。制度を理解し、積極的に活用することで、経済的負担を軽減することができます。ここでは、私たちが実際に利用している制度や、知っておくと便利な制度についてご紹介します。
日常生活用具給付等事業
日常生活用具給付等事業は、在宅での生活に必要な用具の購入や貸与を支援する制度です。対象となる用具や条件は自治体によって異なるため、お住まいの地域の窓口に問い合わせてみましょう。経済的な負担を軽減してくれるので、ぜひ活用したい制度の1つです。私たちは、吸入器や吸引器などの医療機器などの給付を受けています。
補装具費支給制度
補装具費支給制度は、障がいのある方が、日常生活や職業生活に必要な補装具を購入する際に、費用の一部を助成する制度です。私たちは、座位保持装置や車椅子などの補装具の給付を受けています。補装具は、お子さんの成長に合わせて、定期的な見直しが必要になります。
令和6年4月から、障害児の補装具費支給制度の所得制限が撤廃され、すべての障害児について補装具費の支給対象となりました。
障害児福祉手当
障害児福祉手当は、日常生活において常に介護を必要とする重度の障がいを持つお子さんを対象としており、経済的な負担を少しでも軽減するために設けられています。手当の対象となる障がいの程度や状態については、医師の診断書や認定審査によって判断されます。また、児童が施設に入所している場合や、他の公的年金・手当を受給している場合は、支給対象外となることがあります。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、障がいのある児童を養育している方に支給される手当です。この手当は、お子さんの障がいの程度によって支給額が異なります。申請には、医師の診断書が必要になりますので、早めに準備をしておきましょう。
↓令和6年4月以降の月額と支払日
| 障がい等級 | 1級 | 2級 |
|---|---|---|
| 手当の月額 (1人当たり) | 55,350円 | 36,860円 |
| 支払期 | 支払日 | 対象月 |
|---|---|---|
| 12月期 | 11月11日 | 8月分から11月分 |
| 4月期 | 4月11日 | 12月分から3月分 |
| 8月期 | 8月9日 | 4月分から7月分 |
その他利用可能な福祉サービス
その他にも、在宅看護で利用できる福祉サービスはたくさんあります。例えば、ショートステイ(短期入所)や、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)などがあります。ショートステイを定期的に利用することで、介護疲れを軽減することができたり、障害児通所支援では、集団活動を通して、お子さんの成長を促すことができます。
まとめ

在宅看護は、決して楽な道のりではありません。しかし、家族みんなで力を合わせ、専門家のサポートを受けながら、お子さんの成長を支えることができます。この記事が、同じように悩んでいるパパ・ママの、少しでもお役に立てれば幸いです。私たちも笑顔を忘れずに、家族みんなで、この道を歩んでいきたいと思います。

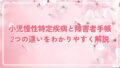
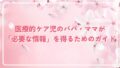
コメント