「小児慢性特定疾病」とか「障害者手帳」とか、初めて聞くと「?」ってなりますよね。うちの子も医療的ケアが必要で、これらの制度について色々調べてきました。同じように悩んでいるパパ・ママのために、少しでもお役に立てたら嬉しいなと思って、この記事を書きました。今回は、これらの制度の違いを、できるだけ分かりやすくお伝えします。
小児慢性特定疾病(しょうにまんせいとくていしっぺい)とは?
小児慢性特定疾病は、小さいお子さんが長く付き合っていくことになるかもしれない、特定の病気のことです。この制度は、病気と闘うお子さんと、そのご家族を応援するためにあります。医療費の負担を少しでも減らして、安心して治療に専念できる環境を整えることを目指しています。
対象疾患一覧と認定基準
小児慢性特定疾病の対象となる病気は、国が定めていて、たくさん種類があります。例えば、がん、慢性腎臓病、慢性心臓病、内分泌疾患、免疫疾患など、本当に様々な病気が対象です。認定基準は、病気の種類や症状の重さによって異なり、お医者さんの診断書や検査結果に基づいて審査されます。
認定されるためには、病気が長期間にわたって治療が必要であることや、日常生活に支障があることなどが条件となります。これらの基準を満たすことで、医療費助成制度を利用できるようになります。
2023年11月時点で、小児慢性特定疾病の対象となる疾病は788疾病、16の疾患群に分類されており、各疾病には対象基準が定められています。
医療費助成制度の内容と対象者
医療費助成制度では、医療費の自己負担額の一部、または全部が助成されます。助成される範囲は、医療費だけではなく、入院時の食事代や、訪問看護の費用なども含まれる場合があります。所得に応じて自己負担額の上限が設定されていて、経済的な負担を軽減しながら、必要な医療を受けることができるようになっています。
小児慢性特定疾病の医療費助成制度では、予め都道府県知事等に指定された「指定小児慢性特定疾病医療機関」が行う医療が助成対象となるため、事前に確認するようにしましょう。
申請方法と必要書類
小児慢性特定疾病の医療費助成を申請するには、まずお医者さんに診てもらって、診断書を書いてもらう必要があります。その他にも、申請書や、世帯の所得を証明する書類などを準備して、お住まいの自治体の窓口に提出します。申請から認定までには、少し時間がかかる場合があるので、早めに手続きを進めるのがおすすめです。申請に必要な書類や手続きについては、自治体の担当窓口で、詳しく教えてもらえます。
障害者手帳とは?

障害者手帳は、身体や知的、精神に障害がある方が、その障害を証明するために持つ手帳です。手帳を持っていると、色々な福祉サービスや税制上の優遇措置、公共交通機関の割引などが利用できる、私たち家族にとって、とても心強い味方です。特に、障害のあるお子さんの場合、社会参加を促進し、より豊かな生活を送るための大切なツールとなります。
手帳の種類と特徴
障害者手帳には、主に3つの種類があり、それぞれの手帳で、受けられるサービスや支援内容が異なるため、ご自身やお子さんの状況に合わせて、適切な手帳を選ぶ必要があります。
- 身体障害者手帳:視覚、聴覚、肢体などに障害がある方が対象
- 精神障害者保健福祉手帳:精神疾患により日常生活や社会生活に制限がある方が対象
- 療育手帳:知的障害のある方が対象
等級ごとの支援内容
障害者手帳には、障害の程度に応じて等級が分かれていて、等級ごとに受けられる支援内容が異なります。例えば、身体障害者手帳では、1級から7級まであり、等級が重いほど、受けられる支援が多くなります。具体的な支援内容としては、医療費の助成、福祉サービスの利用、税金の減免、公共交通機関の割引などがあります。
申請方法と必要書類
障害者手帳の申請には、お医者さんの診断書や、所定の申請書が必要です。身体障害者手帳の場合は、指定医の診断書、精神障害者保健福祉手帳の場合は、精神科医の診断書が必須です。療育手帳の場合は、児童相談所や知的障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。
申請書と必要な書類を準備して、お住まいの自治体の福祉窓口に提出します。審査の結果、手帳が交付されるまでには、少し時間がかかる場合があるので、早めに手続きを進めることをおすすめします。
小児慢性特定疾病と障害者手帳の違い
小児慢性特定疾病と障害者手帳は、どちらも病気や障害のある方をサポートするための制度ですが、対象となる疾病や障害の種類、受けられる支援内容が異なります。これらの制度の違いを理解することで、お子さんに必要な支援を、より適切に選択できるようになります。
支援対象となる条件の違い
小児慢性特定疾病は、特定の病気を持つお子さんを対象とした、医療費をサポートする制度です。病気の種類と重症度が、認定基準となります。一方、障害者手帳は、身体、知的、精神に一定の障害がある方を対象としていて、障害の種類と程度が、認定基準となります。
つまり、小児慢性特定疾病は「病気そのもの」が対象なのに対し、障害者手帳は「障害による日常生活への影響」が対象になるという違いがあります。
利用できる支援制度の比較(医療費助成、福祉サービスなど)
小児慢性特定疾病では、医療費の自己負担額を助成することが主な支援内容です。一方、障害者手帳では、医療費の助成に加えて、福祉サービスの利用、税制上の優遇、公共交通機関の割引など、幅広い支援を受けることができます。
小児慢性特定疾病の医療費助成制度は、医療費に特化した支援であるのに対して、障害者手帳は、生活全般をサポートする制度と言えます。
両方の制度を同時に利用するケース
小児慢性特定疾病と障害者手帳の両方の条件を満たす場合、両方の制度を同時に利用することができます。例えば、特定の慢性疾患を抱え、日常生活にも支障が出ているお子さんの場合、医療費の助成を受けつつ、障害者手帳を活用して福祉サービスを利用することもできます。両方の制度をうまく活用することで、より充実したサポートを受けることができます。
まとめ

この記事では、小児慢性特定疾病と障害者手帳の違いについて、詳しくお話してきました。どちらの制度も、お子さんの成長を応援し、生活をサポートするための、大切な制度です。小児慢性特定疾病は、特定の病気を持つお子さんの医療費の負担を軽減する制度で、障害者手帳は、障害のある方の生活全般をサポートする制度です。
お子さんの状態や状況に合わせて、適切な制度を利用することで、より安心して生活できるようになります。これらの制度を理解し、活用することで、お子さんの成長を一緒に見守っていきましょう。もし、何か分からないことや、不安なことがあれば、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口へ相談してみてください。

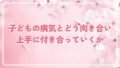
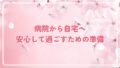
コメント